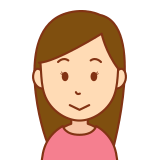
まだまだお出かけできるご時世ではないので、おうちで子供と楽しく学習できる方法を探しています。
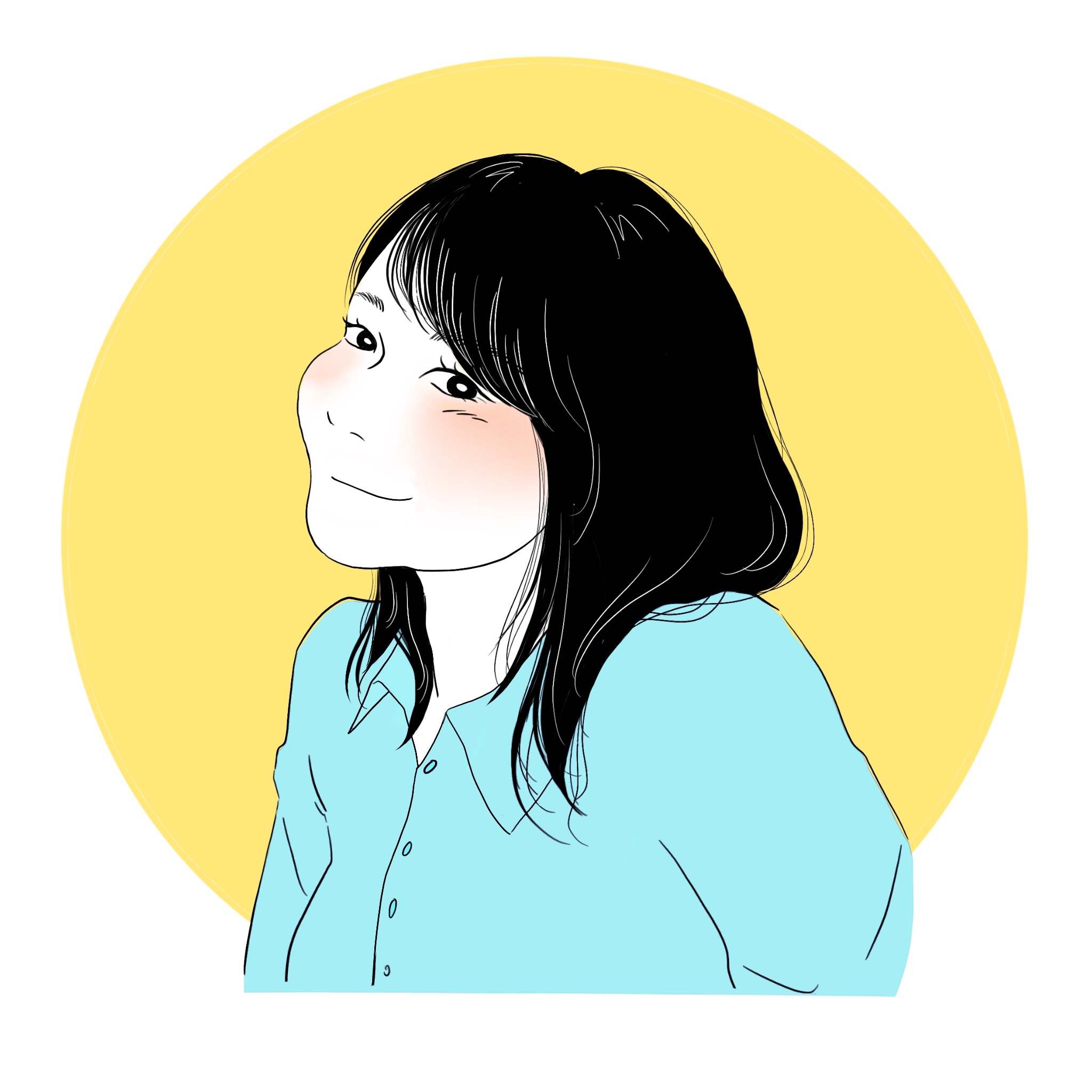
中学年の子が親子で楽しく学べるコンテンツを紹介します。
学んだことは、ミニ自由研究のようにして、親子で分かりやすくまとめましょう。
小学校高学年になると、塾や習い事で土日に家族でゆっくりする時間が減ってしまいます。
中学年のうちに苦手教科を作らないように、興味関心を広げておくことが大切です。
親子でノートや画用紙にわかったことをまとめる活動をすることで、学びがより深まります。
おうちミニ報告会を開けば「話す力」も身に付きますね。(オンラインでおじいちゃん、おばあちゃんに参加してもらうと緊張感も出ます!)
おうち理科実験にチャレンジしよう
お茶の水女子大が提供しているこちらのサイトでは、簡易的な理科実験の方法が学年別に紹介されています。
学年にとらわれず、子どもの作ってみたい実験道具を作ってみてください。
学校の実験器具を用いた実験とは、違う楽しみを感じることができます。
行った実験について、準備した材料や、実験の手順、実験結果をまとめて、報告しましょう。
実験器具づくりはほとんど、親がやっていたなんてことでも楽しい思い出になり、エピソード記憶につながります。
慣用句を使って漫画を描こう
「ことば食堂へようこそ」は、文科省が「国語に関する世論調査」の結果を基に、慣用句等を使用する上でコミュニケーション上の齟齬(そご)が生じる場面や、慣用句等の本来の意味、本来とは異なる意味の生まれた背景等を動画で紹介したものです。
テレビの雑学番組では、右から左へと流れてしまう情報も、「これで漫画を描く!」となるとやる気がアップし、理解しようと映像に集中してくれます。
気になった慣用句の動画を気のすむまで視聴し、紙芝居や4コマ漫画にしてまとめることで知識が定着したり、使い方を考えたりすることができます。
同じ慣用句を使った4コマ漫画を、家族でそれぞれ描くのもおもしろいですよ。
統計グラフを作ってみよう
※令和2年度は、東京都主催の統計グラフコンクールは実施されませんでした。
「統計」と一言で言っても、棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフなど、表し方はそれぞれです。
私が教員をしていて、中学年がつまずく点が、調べ学習はできるのに表現の仕方がわからないというところでした。
中学受験のために塾に通っていて、知識のインプットはよくできているものの、人にわかりやすく表現することは練習不足な子も多かったです。
結果、調べ学習をしっかりできたものの、教科書とそっくり同じまとめの形で満足する子が多くいました。一人ひとりに時間をとってあげられたら、もっとよいまとめ方になるのにと思うことも多々ありました。
データ集めは、おうちの方が担当するのがおすすめです。
家の周りの地図をつくろう
この国土地理院のサイトでは、地図の書き方について
方位
距離・縮尺
地図記号
が必要であることをわかりやすく示してくれています。
学校までの道のりを、子どもと一緒に散歩しながら歩数を数え、建物を確認しましょう。
正確な地図でなくても、縮尺の計算や地図記号を書く経験ができ、知識につながります。
昔のくらしを調べてみよう
こちらのパナソニックのサイトでは、各年代ごとのくらしと家電が紹介されています。
両親や、祖父母の時代の話を直接聞くことができるのは子どもにとってうれしいものです。
あらかじめサイトの情報を読み、調べることを親子で整理しましょう。
台所のこと
洗濯のこと
電話のこと
自動車のこと・・・など
両親はもちろん、おじいちゃんおばあちゃんに取材(電話など)すると、理解を深めることができます。(おじいちゃん、おばあちゃんも学習の手伝いになって、声も聞けて大喜びでしょう!)
最後に
どの学習ネタも、インプットとアウトプットを親子で一緒にやりましょう。
たまに「親が手を出したら、子供の成果にならない」と言う人がいますが、賞に入賞するために学ぶのではないですから、初めはまとめ方を教えてあげることが大事です。
中学年の子供は、学校で、わかったことを新聞やリーフレットにまとめる活動を経験しています。
おうちで一日でできる簡単なもので、外に出すわけではないので簡単なものでいいのです。
子どもが家庭でまとめ方を経験していることによって、学校などの発表の場で自信をもって表現することができます。
大切なのは、楽しく学ぶということです。
その積み重ねが子供の「もっと知りたい」という知的好奇心につながっていきます。
お子さんが興味をもって取り組めるものが見つかれば幸いです。

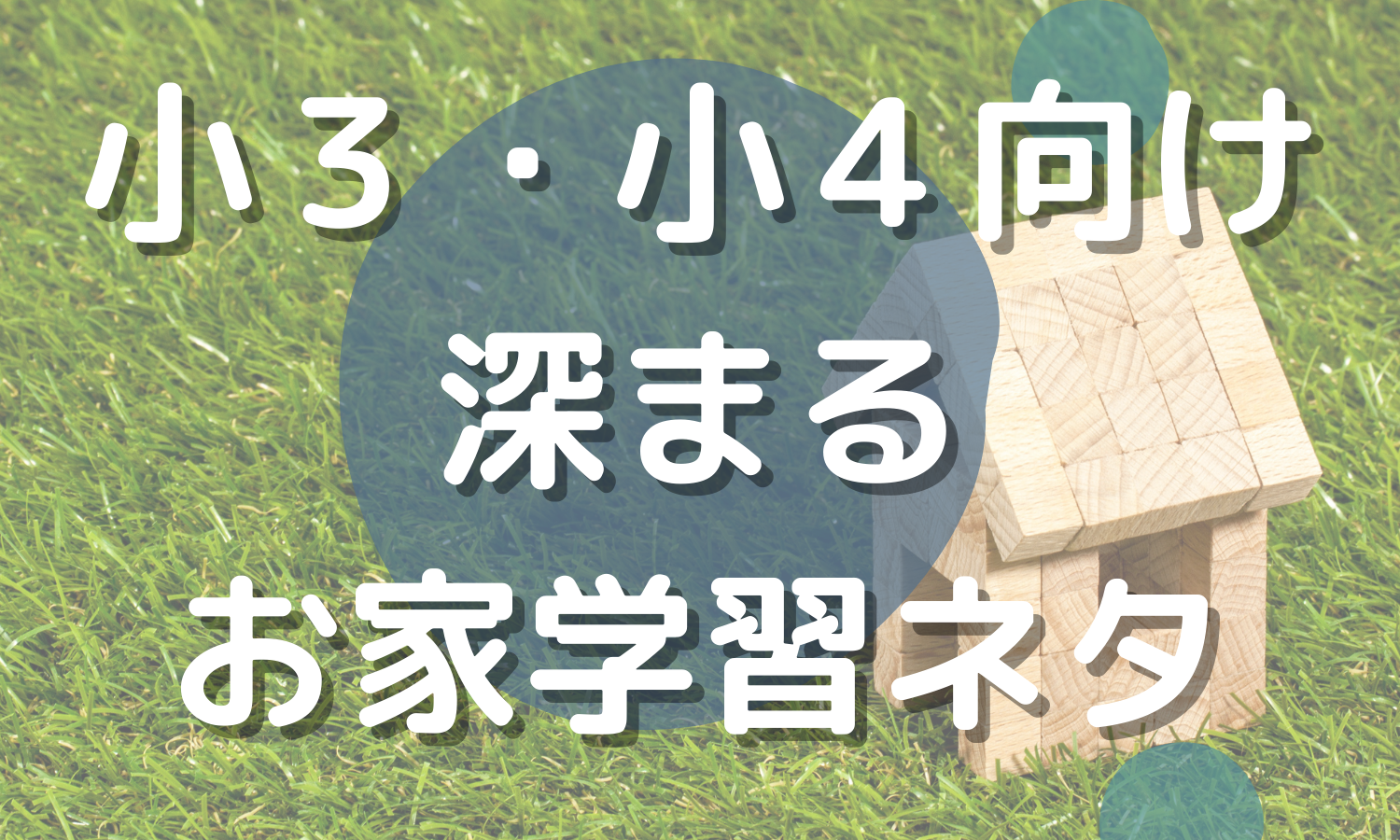

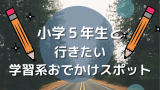
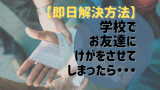
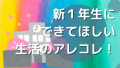
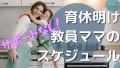
コメント